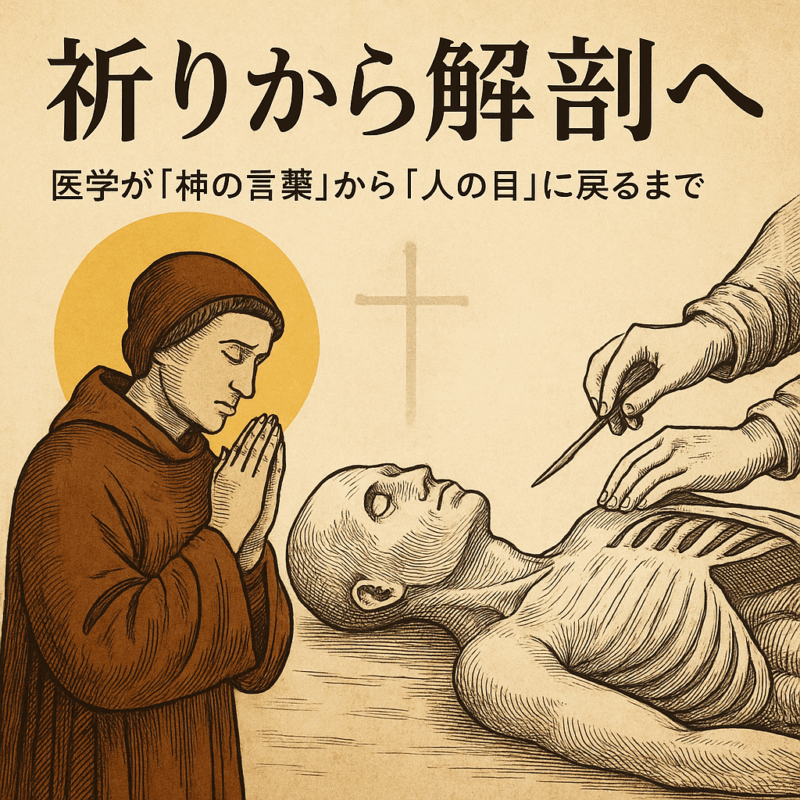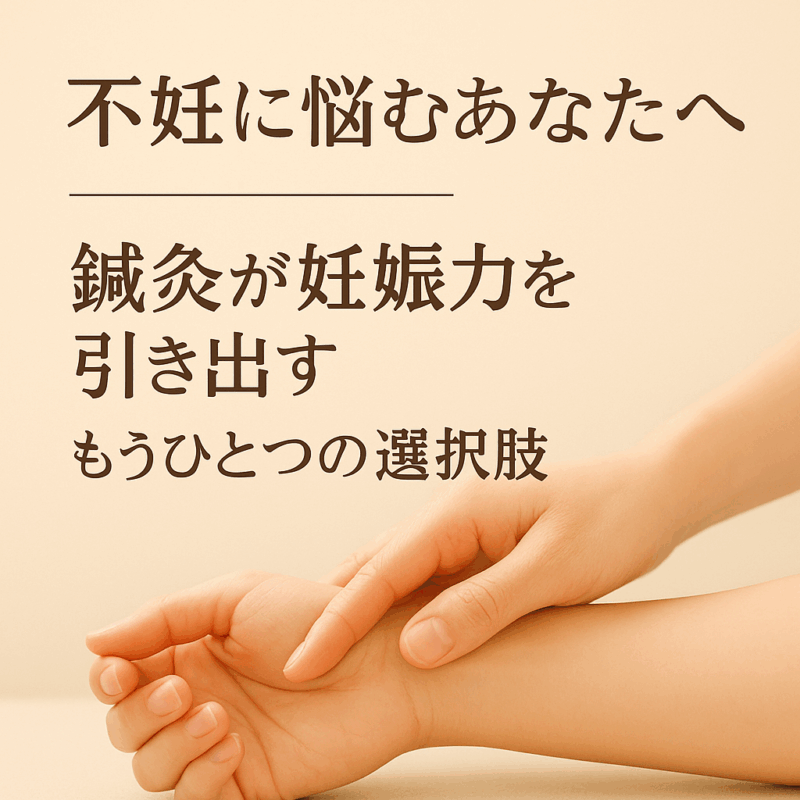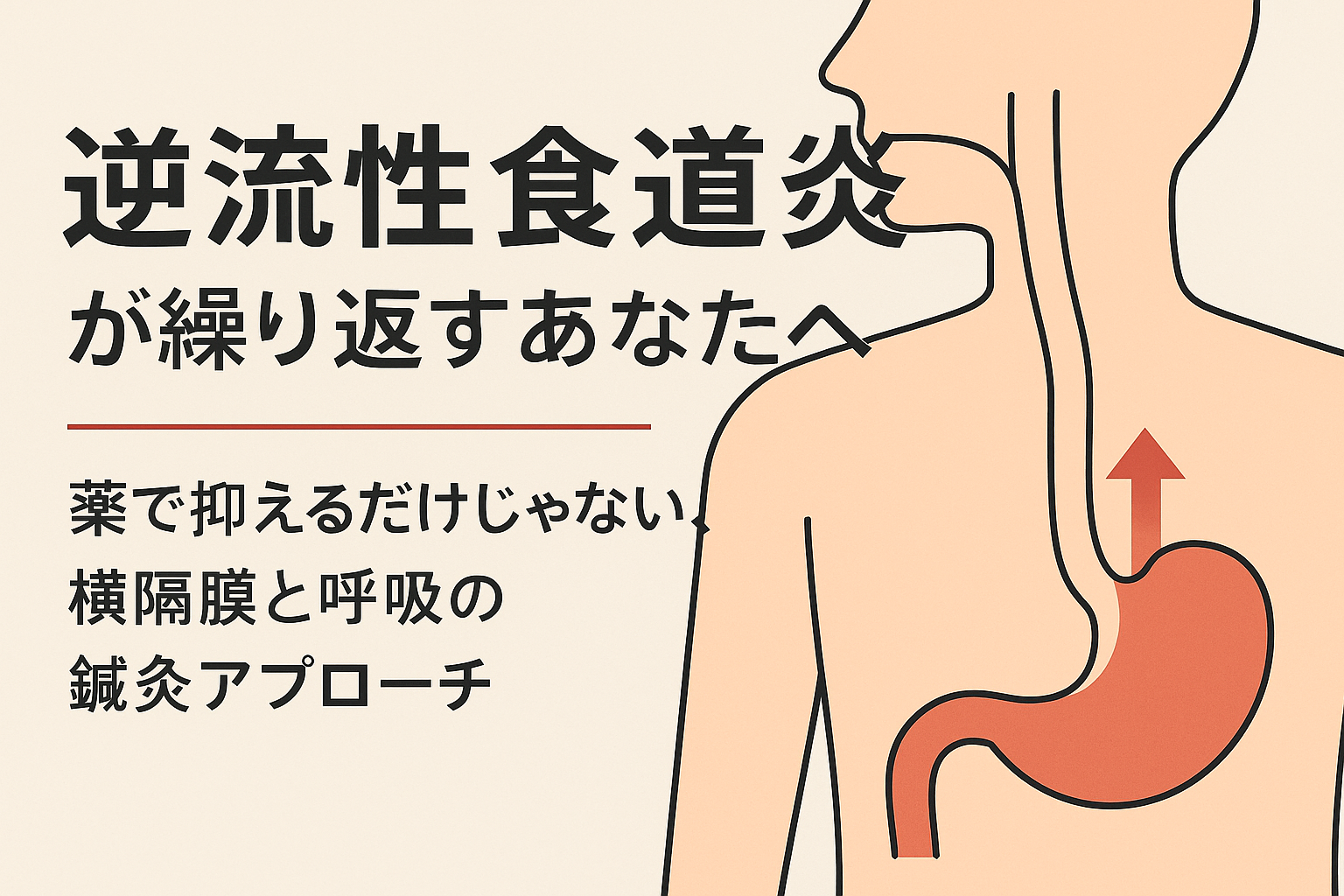
―薬で抑えるだけじゃない、横隔膜と呼吸の鍼灸アプローチ―
「また胸やけが…」その不快感、実は“息苦しさ”のサインかもしれません。
なんとなく胸がつかえる。
食後になると、喉まで酸っぱいものが込み上げる。
薬を飲んでいるけど、また症状がぶり返してくる。
そんな「逆流性食道炎」に悩まされている方が、私たちの鍼灸院にも多くいらっしゃいます。
けれど、話をよく聴いてみると──
「最近、深く息が吸えない気がする」
「常に力が入っていて、抜き方がわからない」
そんな“呼吸の不調”を感じている方がとても多いのです。
逆流性食道炎とは?|薬で抑えても治りきらない理由
逆流性食道炎(GERD)は、胃酸や胃の内容物が食道に逆流することで、胸やけや呑酸(すっぱい液が上がってくる感覚)などを引き起こす病気です。
原因とされるのは、
- 胃酸過多
- 下部食道括約筋のゆるみ
- 食後すぐの横になる習慣
- 脂っこい食事や過食
- ストレスや自律神経の乱れ
などが挙げられます。
一般的にはPPI(プロトンポンプ阻害薬)などの薬で酸を抑えますが、
「やめるとまた再発する」
「飲み続けることに不安がある」
という声も、少なくありません。
東洋医学の視点から見る、逆流性食道炎
東洋医学では、逆流性食道炎のような状態を
- 胃気上逆(本来下に流れるべきエネルギーが上に向かう)
- 肝胃不和(ストレスが胃の働きを邪魔する)
と捉えます。
つまり、“胃酸”という結果だけを見るのではなく、
なぜ胃の動きが乱れたのか?
なぜ今、上に向かっているのか?
という背景に、体全体のバランスの乱れを探るのが鍼灸の役目です。
鍵は「横隔膜」にありました。
横隔膜は、胸とお腹を分ける“膜状の筋肉”です。
この横隔膜の真ん中にある穴(食道裂孔)を食道が通って胃へと続いています。
本来、横隔膜の張力によってこの裂孔はしっかり締まり、
胃酸の逆流を防ぐ“弁”のような役割を果たしています。
しかし、
- 姿勢の悪さ(猫背・反り腰)
- 呼吸の浅さ(ストレス・過緊張)
- 体幹の硬さや腹圧の変化
などで横隔膜の機能が低下すると、
この「弁」が緩みやすくなり、逆流が起こりやすくなるのです。
鍼灸でできること|“呼吸”と“構造”を整える
鍼灸では、横隔膜そのものには直接刺激しませんが、
呼吸に関係する筋肉や、横隔膜を支配する神経(横隔神経・自律神経)に働きかけていきます。
呼吸に関わる胸郭や腹部の緊張を緩めながら、
“息を深く吸える身体”を取り戻すことが、逆流性食道炎の根本改善につながるのです。
実際の症例|「息が戻ったら、食後の不快感も消えました」
40代・女性。
長年、逆流性食道炎に悩み、薬が手放せなかった方が来院されました。
初診では、胃の張りよりもみぞおちと横隔膜の硬さが目立ち、
呼吸も浅く、肩で息をしている状態。
3回目の施術後、こんな言葉をくださいました。
「ご飯のあとが楽になりました。それと…息が深く吸えるようになってきた気がします」
薬で症状を“抑える”のではなく、
身体全体が“戻る”ように働きかけていく──
それが、鍼灸の本当の力だと感じています。
まとめ|症状は「身体からの優しいメッセージ」
逆流性食道炎は、ただの胃の問題ではありません。
それは「今のままで本当に大丈夫?」という、
身体からの小さなサインかもしれません。
鍼灸は、薬とは違ったかたちで、
呼吸を整え、緊張をゆるめ、自律神経を整えるという“からだの根っこ”にアプローチします。
薬をやめたい方
再発を繰り返している方
“整える”という選択を探している方へ
逆流を止めるのではなく、「流れを取り戻す」ための鍼灸。
ぜひ一度、体験していただけたらと思います。
ずっとご不安を抱えたまま、
治療院探しに時間とお金をかけるのは
最後にしてほしい。
ぜひ辛い症状やお悩みを
ご相談ください。
03-6823-4230
受付時間:9:30~21:00
LINEのメッセージでもご予約を承ります