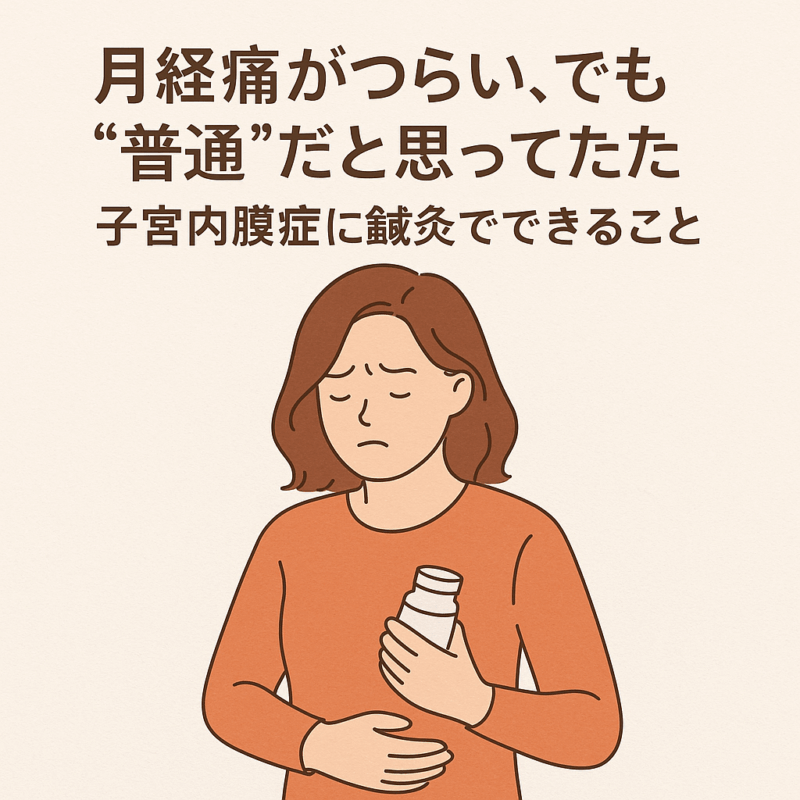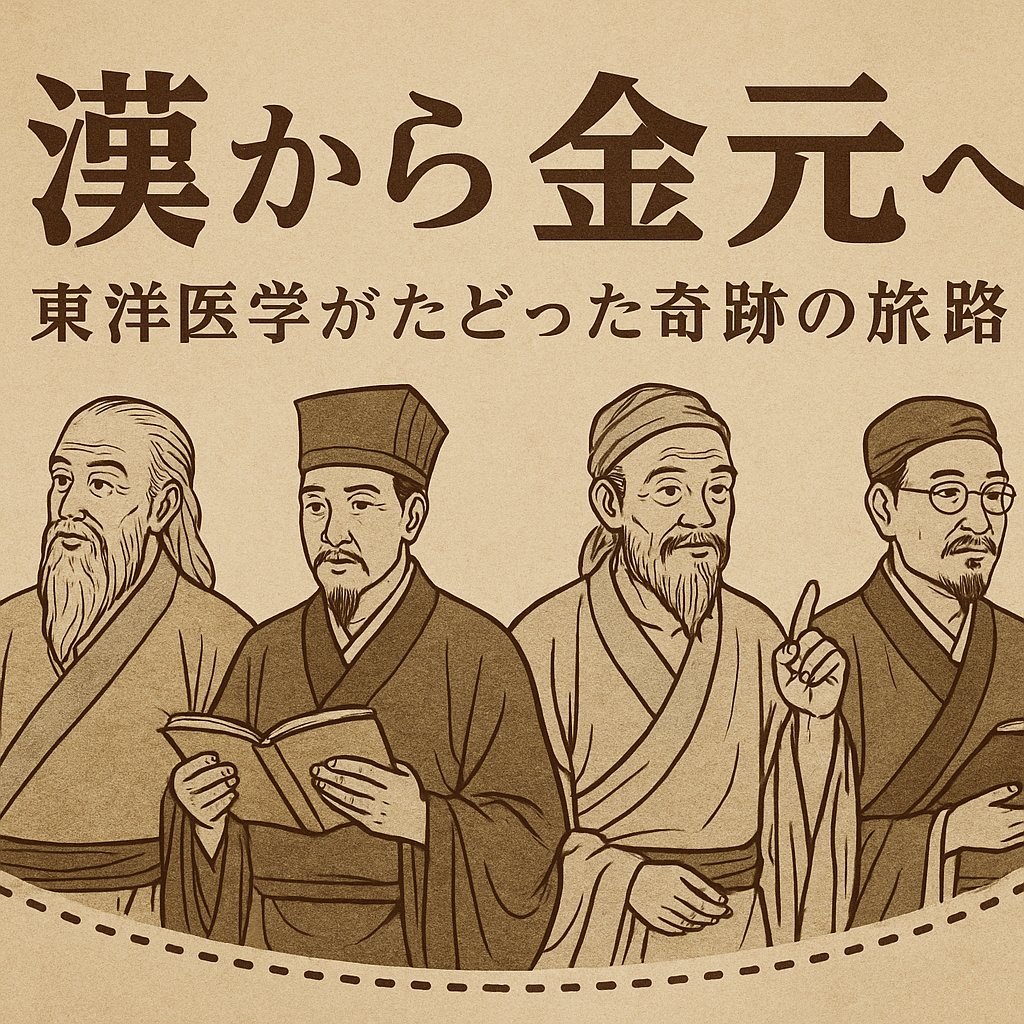
こんにちは院長の山元です
「東洋医学って、いつからあるんですか?」
この質問をいただくたびに、一つの壮大な“歴史”を思い浮かべます。
それは、単なる「治療の歴史」ではありません。
人が人を癒そうとした心の奮闘録であり、世界と身体をどう理解するかの探究の物語。
本記事では、東洋医学の黎明期である「漢」から、思想が花開く「金元」までを、
ストーリー仕立てでやさしく、わかりやすく解説していきます。
どうぞ、2000年の歴史へご案内させてください。
第一章|漢――宇宙と身体をつなぐ設計図
中国が初めて統一された時代、
医学は「神の言葉」から「自然の理」へと姿を変えていきました。
この時代に生まれたのが、医学のバイブル『黄帝内経』。
陰陽・五行・経絡――それはまるで宇宙の設計図をもとに人を診る学問でした。
さらに後漢末には、張仲景が『傷寒論』を著し、疫病や発熱などに対する診断と治療の理論を確立。
医学がはじめて「読み解き、治すもの」になった時代です。
第二章|魏晋南北朝――理屈では救えない命と向き合って
漢が崩壊し、時代は混乱の中へ――
この時代、人々は「理論」よりも「信仰」や「超越」を求め始めました。
- 道教の錬丹術は、不老不死の薬を目指し
- 仏教は「病は因果によって生じる」と語り
- 医術はオカルトや儀式と混ざりながら、多様化していきました。
医は、“哲学”から“信仰”へと揺れたのです。
葛洪や陶弘景のような医僧・道士たちが活躍し、
この時代に独特な“心と体をめぐる神秘主義的な医学”が花開きました。
第三章|唐――乱世の知をまとめ、文化に変えた名医の登場
唐代は、再び統一された国家のもとで文化が開花。
この時代、医学は再び国家のもとで体系化され始め、
その象徴が**孫思邈(そんしばく)**です。
「大医はまず人の心を癒す」
そう語る彼は、道教・仏教・民間療法の知識を融合させ、
『千金要方』という医学の大百科事典を編纂しました。
医が“学問”から“人の道”へと深化した時代。
信仰と実践、東洋の叡智が一人の医師によって再統合されたのです。
第四章|宋――医学が市民のものになった瞬間
印刷技術の発展とともに、国家は動きました。
「医術を、すべての人のために。」
- 医学校「太医局」の設立
- 『和剤局方』『太平聖恵方』などの処方集を全国に印刷・配布
- 医師の資格試験の導入
これにより、医学は仙人のものでも、貴族のものでもなく、町の人々のものになりました。
医学が初めて「制度」として整い、
専門職としての“医者”が社会に根づいていったのです。
第五章|金元――医が哲学になった時代
宋で整えられた医療制度と出版文化の上に咲いたのが、
思想としての医学でした。
- 劉完素:「病の根は“火”。冷やせば治る」
- 張従正:「とにかく出せ。汗・吐・下!」
- 李東垣:「脾胃が弱ってる。補え!」
- 朱丹溪:「陰が足りない。ストレスと心に注目せよ」
彼ら“金元四大家”は、それぞれ異なる身体観・病理観を持ち、
治療の方法論ではなく、“病とは何か”そのものに挑んだのです。
医が“道具”ではなく、“思想”へと昇華した時代。
治すことは、生きることを問うことと同義だったのです。
【結び】医は“人を想うこと”から始まっていた
2000年の旅路を経て、今もなお東洋医学は生きています。
自然と体のつながり、心と病の関係、そして人が人を想うことの力。
漢から金元までの歴史は、それらを丁寧に編み込んできました。
医とは、術ではなく「想い」なのだ。
そう語りかけてくれるこの歴史が、
現代を生きる私たちにとって、なにかの“処方箋”になることを願っています。
お読みいただきありがとうございました。
山元大樹