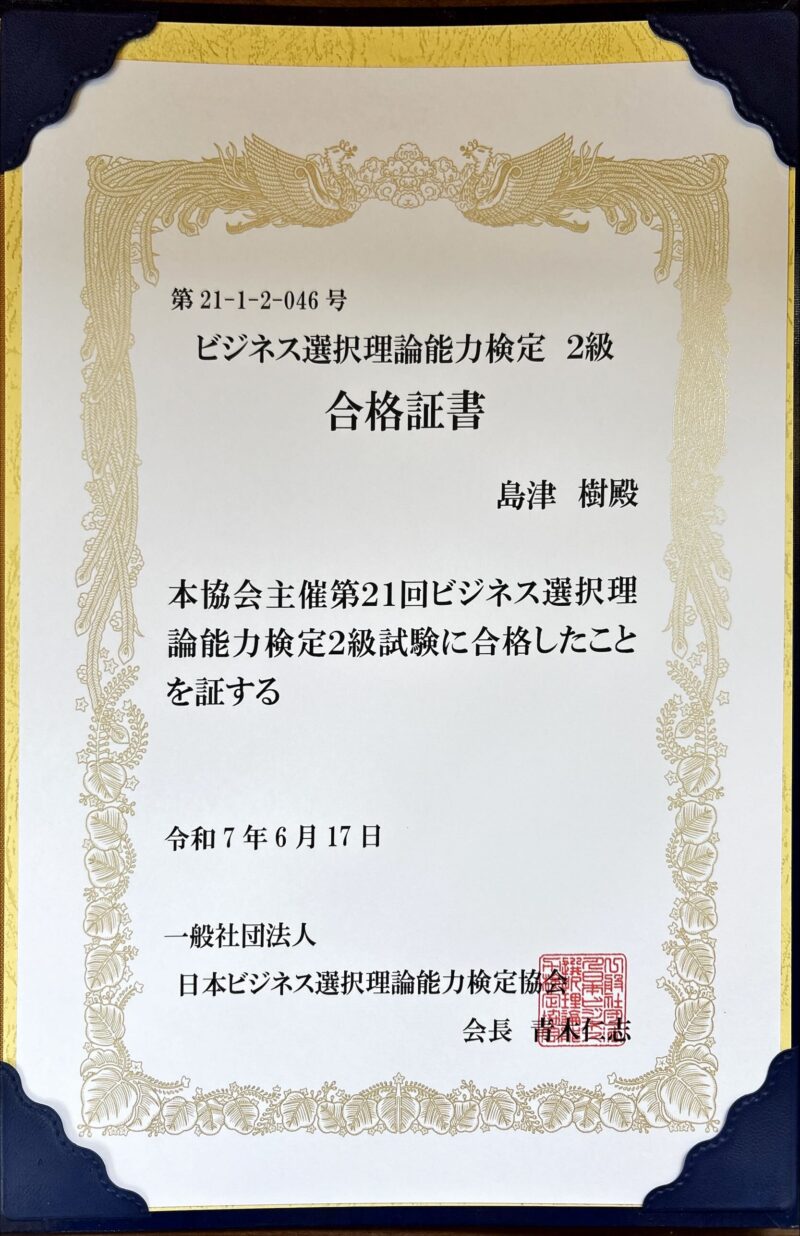こんにちは!寺嶋です!
先日社員のみんなで江ノ島にある、杉山和一のお墓にお参りに行ってきました。
そもそも杉山和一って?
杉山検校は江戸時代の鍼灸師であり、本名は杉山和一(わいち)といいます。
検校とは、盲人の役職の最高位の名称です。現在の日本鍼灸の礎を築いたのが杉山検校です。和一は幼少期にかかった伝染症が原因で失明してしまった養慶は当道座に入門し琵琶法師としての修行に入り、一方流(いちかたりゅう)を学び、15歳の時に師から「和一」の名前を与えられました。
琵琶法師としての修行を続けていた和一でしたが、盲目の鍼医である山瀬琢一の存在を知り、鍼に興味を持ちます。山瀬は同じ当道座の琵琶法師でその後鍼の修行をして江戸で鍼医として活躍していました。
鍼医として世間の役に立ちたいと思い立った和一は17歳の時に山瀬琢一に弟子入りを果たします。しかしながら不器用で技術が向上しなかった和一は師から破門され、なんとしても鍼医として成就したいという思いで江の島弁財天を参拝し岩屋にこもり断食修行を行いました。
終わった帰り道、石につまずき転んでしまいます。その時、わらをもつかむ気持ちで「葉っぱにくるまれた松葉」を握りしめます。
それを見て鍼を管に入れ叩く方法、つまり「管鍼法」を思いついたのです。その後「管鍼法」を練習をし鍼技術がみるみるうちに上達していきます。
和一75歳の頃、五代将軍の徳川綱吉公がぶらぶら病 (現在のうつ病) にかかってしまい、あらゆる治療を試しますが一向に治りません。綱吉公は和一の噂を聞き鍼治療をしてもらうことになります。
綱吉公のぶらぶら病は和一の数回の鍼治療で治ってしまいます。治療の御礼として和一は本所(東京都墨田区)に豪邸をもらい、盲人としては最も位の高い関東総検校に任命されたと言われています。
そんな和一さんのところへみんなでお参りに行きました。
鍼灸を日本に残し、広めてくれた和一さんには本当に感謝です。
現在、日本の鍼灸の受療率は5%程度です。
私たちは先人が残してくれた鍼灸という素晴らしい技術を後世に残していくためにも目の前の患者さんお一人お一人に向き合い続け感動を提供できるよう精進してまいります。
お参りに行き、改めて気が引き締まりました。
私は歴史上の人物で西郷さんも好きなのですが、西郷さんも子供の頃に腕を負傷し、武士道を諦め、学問の道への進んで死ぬまで日本をよりよくするために生きていました。
何かを成し遂げる人は何かを失った経験がある。
その経験を何かのせいにすることは簡単ですが、それを失ったことによって他のことが研ぎ澄まされる可能性はたくさんあります。
身体に何か症状が出てきているということは何かを教えにきてくれているかもしれません。
その何かをあなたと考えていきたいと思っています。
今何か病や症状に悩んでいらっしゃる方は一度、鍼灸院ひなたへご相談いただければと思います。
本日も最後までお読みいただきありがとうございます🙇♀️